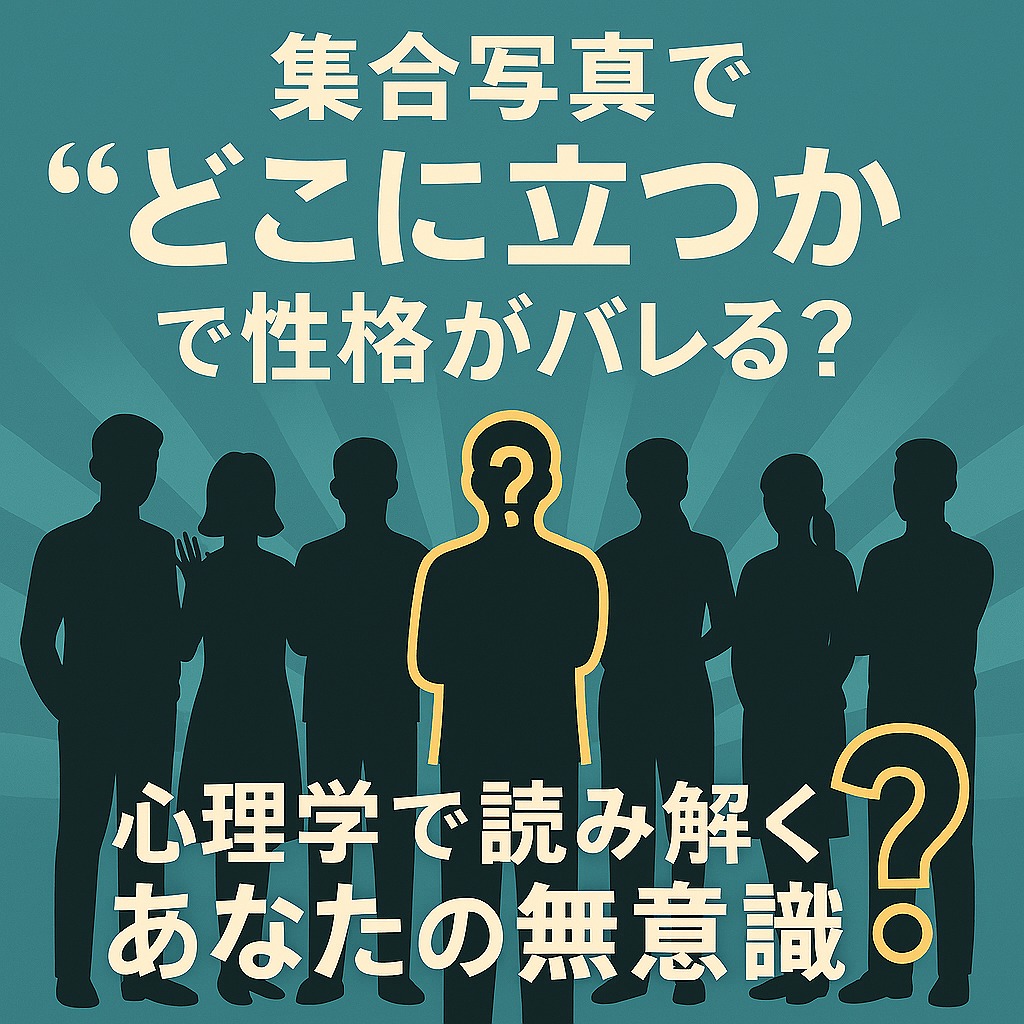教えるとき、まず何をしますか
何かを教えるときに、してしまいがちなのは、答えのみ教えたり、どのようにして行動するかのみを教えてしまいがちですが、これでは、教えらえた側には、しっかりとは伝わりません。
例えば、算数でも「2×3は6です。」と数字を並べるだけで教えても、教えられた側は数字だけが頭の中に入り、なぜ6になるかが理解できていません。
教えるときは、その結果となる理由とイメージが頭に浮かぶように伝えるのです。
2×3の時も、丸二つづつあるグループが3あるから6(〇〇、〇〇、〇〇)と見てイメージがわくように理由を付けて教えるとより、理解しやすくなります。
これは、記憶に残す時も有効で、ただ言葉や数を反復的に覚えるより、ストーリーやイメージに関連付ける方が記憶に残る「精鋭化リハーサル」という方法です。
また、記憶は話の最初と最後の部分が残りやすくなっているため、最初に覚えてほしい部分を伝え、途中でその理由や過程を伝え、最後にまた、覚えてほしい部分を再度伝えてあげることでより、記憶に残るようになります。
次に教える時間です。
人間は最高の集中力を保てる時間は15分と言われています。
教えるときは、15分以内を目標に計画を立てると良いでしょう。

教えた後の行動
教えた後は、皆さん相手はもう覚えただろうと思い何もしないことが多いですが、これではせっかく覚えたことも、忘れてしまうかもしれません。
教えた後は相手に覚えたことを、発表してもらったり、問題を解いてもらったり、コメントを書いてもらうようにしてください。
そして、教える前に必ず伝えてください。
そうすることで、相手は「覚えなければならない」と無意識的に自覚するため、より覚えやすくなります。
さらに、発表や問題を解くなどのアウトプットをすることで強固に記憶に残すことができるようなります。
また、記憶は1回ではなく、期間を開けて複数回することで、長く記憶に残るようになります。
これは、脳が重要な記憶と認識するためです。
教えるときは、短時間で複数回行い、その都度、相手に発表などしてもらい、その内容がしっかり頭の中に定着していると判断できれば、完了するのが良い方法です。

優しく教えるのか、厳しく教えるのか
教えた後に、教えた相手が実際に行動した結果に対する評価をどのようにすれば良いでしょうか。
基本的には「褒める」方が、良いと思われますが、これは半分正解です。
なぜなら、褒めることで成長が期待できるのは、「初心者」の時が最も効果があり、上級者にはあまり効果が期待できないからです。
もちろん、上級者に対して、褒めることで相手も悪い気はしないので、褒めなくて良いわけではありません。
上級者にはどのようにするのか、それは厳しいですが「問題点を指摘する」ことです。
アメリカの大学の実験で、語学教室の初級クラスの生徒と上級クラスの生徒に、「褒める」先生と「問題点をしてきする」先生のどちらかが良いかとアンケートを取りました。
結果、初級クラスは「褒める」先生、上級クラスは「問題点を指摘する」先生が半数以上で選ばれていました。
なぜ、上級者は「問題点を指摘する」のが良いかですが、回答者の多くが「どおしたら自分のスキルか改善するか指摘してほしいから」との理由からでした。
これまでは、褒める又は、厳しくするの2択でしたが、実は、非常に身近な相手に対しては、褒めることも、問題点を指摘することも必要ないことがあります。
相手の行動を見守り、その行動に対して、感謝するだけで良いのです。
これは、自分で課題を解決し、自己成長する心を成長させるためです。
褒められて成長した人は、褒められなければ成長しなくなってしまうことがあるからです。
テストで100点を取って、褒められていたのでやる気が出て、次も100点を取った時に、褒められなかったら、認めてもらえなかったと落胆し、その次からは頑張らなくなってしまうことからです。
褒めらえる=頑張るになってしまっていたのです。
本来、自己成長は自分の為であり、誰かに褒められる為ではありません。
ここは、難しいところではありますが、見極めがとても大事です。
簡単な区別としては、関係性で判断するのが良いと思います。
会社は、辞めてしまえば、その関係性は終わります。このような関係性であれば、褒める、指摘する教え方で充分です。
家族であれば、ずっと関係性が続きますので、褒めない、指摘しない教え方が良いと思います。