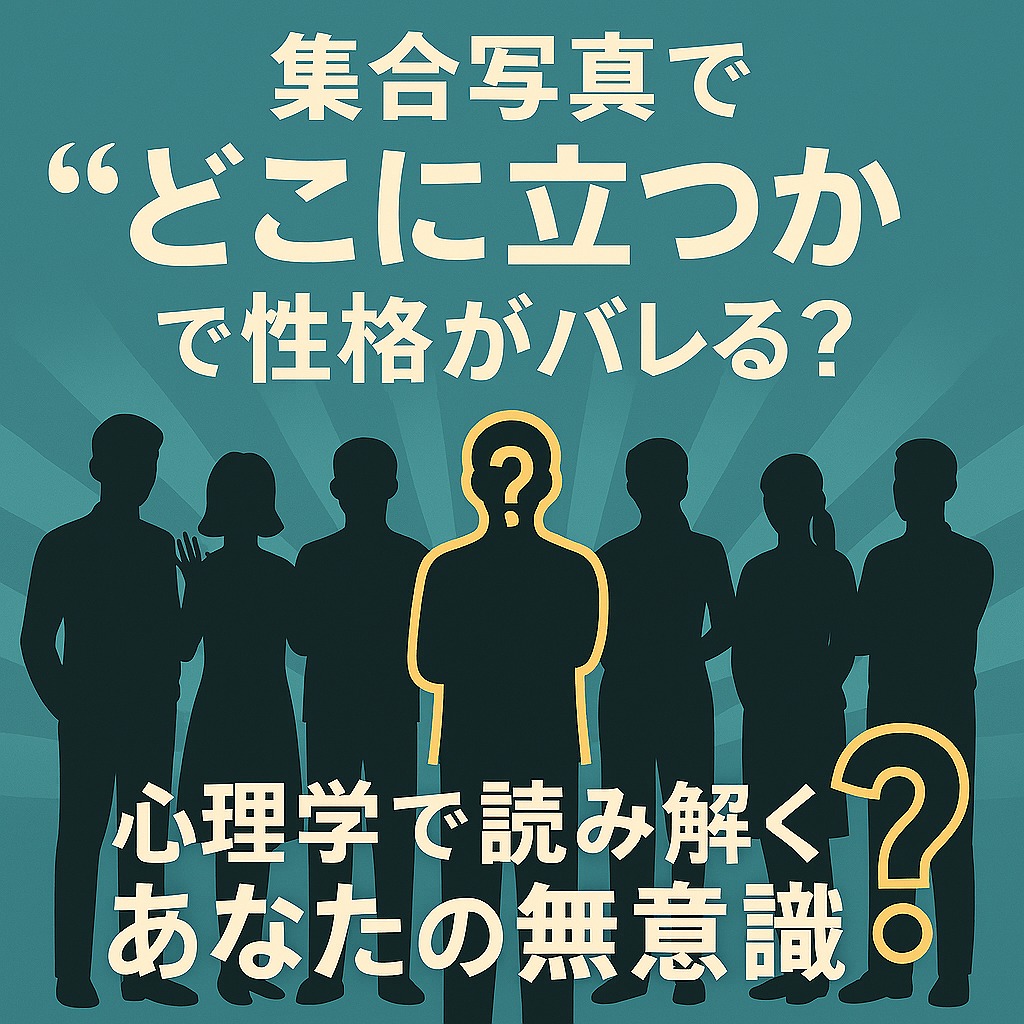会議の質が低いとき
「今日の会議は短く、しっかりとしたい!」と思っているあなたに伝えたい話です。
仕事をすると必ずあるのが会議です。
なぜ会議をするのか、それは自分自身だけでは考えが足りない時や上司などの他者の判断を必要な時があるからです。
でも、この会議、人によっては「また、会議~。いつも、長々とするからウンザリだよ~。」って思われたりします。
それでも行われるのは、会議が一人ではできない案件を進めるために有効な手段だからです。
この有効な手段である会議が、なぜかみんなの足を引っ張ることがあります。
長い会議があった時の記憶を思い出してみてください。
皆さん、何をしていましたか。
その場でいろんなことを話し合ったり、アイデアを出し合ったり、時にはしばらく沈黙があったりしていませんか?
その会議で、いろんな意見やアイデアが出て、最終的に方針が決定すれば、主催者としては開催したかいがあったと思えます。
しかし、時には全くまとまらず、次回の打ち合わせがもう一度決まったりします。
そうなっては、出席者はウンザリ。
やる気も半減し、次の会議もきっと長々と続きます。
いろんな意見やアイデアが出るのは非常に喜ばしいことです。
でも、質の低い会議はできるだけ避けないのが、人の心情です。
質の低い会議の特徴は「その場で」初めて、内容が展開されていることです。

会議の準備とは
あなたは、会議の準備をしてほしいと言われたら何をしますか。
- 会議の議題を決める
- 会議の流れを考える
- 会議に出席するメンバーを決める
- 日程を調整する
- 会議の場所を抑える
- 当日の会議資料を作成する
これくらいは、思いつくと思います。
この準備で会議を行うと、その会議の質はあまりよくないと思います。
「なぜ?」と思う人はいると思います。
なぜなら、先ほども話したように「その場で」初めて、内容が展開されることになるからです。
会議に参加した人たちは、そこで初めて具体的な内容が知らされます。
そして、そこでの発言は、その場で思いついた内容になります。
思いつきだけで始まる話し合いは、大抵まとまりません。
その結果、会議が長くなります。
「それは分かったけど、一体どうすればいいんだ!」と思われた人、良い気づきです。
答えは、「出席者全員が意見をもった状態で会議に出席する」ことです。
それを裏付ける調査がありました。
小学校の授業で2つのグループに分けて、同じ課題について異なる手法で学びました。
- 集団討論形式で課題を学習
- 研究発表形式で課題を学習
この結果、研究発表形式でした方が、全員の理解度が高かったことです。
これは、それぞれが調べて、自分の意見を持った状態で話し合いに参加した結果です。
実は集団討論形式で理解度が低い理由の一つに、「さぼる人がいた」という結果が出ています。
これは、大人の世界でも同じです。
会議でお互いが意見を出し合い、討論していると必ず「さぼる人が」現れます。
話がうまくまとまらないだけではなかったのです。
質の高い会議にするには、「出席者全員が意見をもった状態で会議に出席する」ことが必要ですが、それを実行するにはコツがあります。
- 会議資料は会議の2日以上前に出席者へ事前に配布する
- 会議で求めているアイデアや判断内容を事前に伝える
- 会議出席者には事前に「参加者全員に意見を発表してもらう」と伝える
これを行うと、会議の質はぐっと上がります。
参加者はこの連絡を受けると嫌でも気になります。
「えっ!意見を絶対に言わないといけないの?」と焦り、事前に資料を確認し、なんとなくでも自分の意見を準備することになります。
この何気ない準備が、当日の会議の質を大きく高めます。

会議の質は主催者・出席者の意識次第
ある会社の社員でこんなことがありました。
以前に配属された部署は、客先と直結した最前線の部署いわゆる営業で時間も質も必要な業務がほとんどでした。
そんな中、上司に言われたことが「必ず資料を事前に配布すること」、「その資料の中には必ず、何をしてほしいのか、何を決めてほしいのかを記載すること」、「特に、何か決めてほしい時は、YESかNOだけを言えば終わるような会議もしくは、A案、B案、C案など、どの案か言えば終わる会議にすること」と何度も言われました。
実際に、一通りに準備が終わり会議を始めると、自分が資料の説明を最後までした後に最終判断者が「よしっ、これでいこう!」と発言し、会議はすぐに終わっていました。
仮に、「これではダメだ!」となった時も、「進めていきたいのであれば、追加でこの情報が必要だ」と必ず、明確な指示が出ていました。
その時は、気づかなかったのですが参加者全員が事前に資料に目を通し、自分の意見を持っていたのです。
次に配属された部署は、比較的客先から遠く、社内だけのつながりが多い部署でした。
そこで、会議をするときに言われたのが、「とりあえず、時間と場所だけ抑えておいて」だけです。
なんか前と様子が違うなと思いながら、会議の準備をし、会議の時に初めて資料の配布と説明をしました。
いざ始まると、資料の説明の途中で、「これはどんな意味だ」とか、「そんなことして本当に意味あるのか」、「そもそも、この会議の目的な何だ」などの発言が飛び交い、「あれっ、なんか全然まとまらない。」となったことを今でも覚えています。
「部署が違うだけで会議の質がこんなにも違うのか」とショックを受けたくらいです。
何が違うのか考えてみたら、決定的に違ったのが事前の準備でした。
そこで、事前に資料を配布してみたものの、誰もその資料を読まずに会議に出席してきます。
平然と「今初めて知ったのですが。」と会議中に発言し、周りもそれに同調しています。
元々資料には、会議で求めているアイデアや判断内容を事前に記載しているので、次は会議出席者に事前に「出席者全員に私から意見を求めたいと思っています」と伝えたところ、数人が反応してくれました。
それでもまだ足りないと感じました。
「一体、前の部署と何が違うんだ?」と考えました。
そこで、思い出せたのは会議の前に資料を配布したら、前の部署は事前に私に質問をしてくる人が多かったことです。
会議に参加する前に、疑問や悩む部分を解消してから、参加していることに気づきました。
そこで、事務系の部署で私が試したのは、「ある程度会議の決定権をもつ上司に事前に資料を渡し、その場で説明した」ことです。

その結果、その上司は内容を理解しているため、すぐに会議で判断を行われ、すぐに終わることができました。
その話を聞いて感じました「会議の質は、主催者と出席者全員の準備がとても大事なんだ」と。